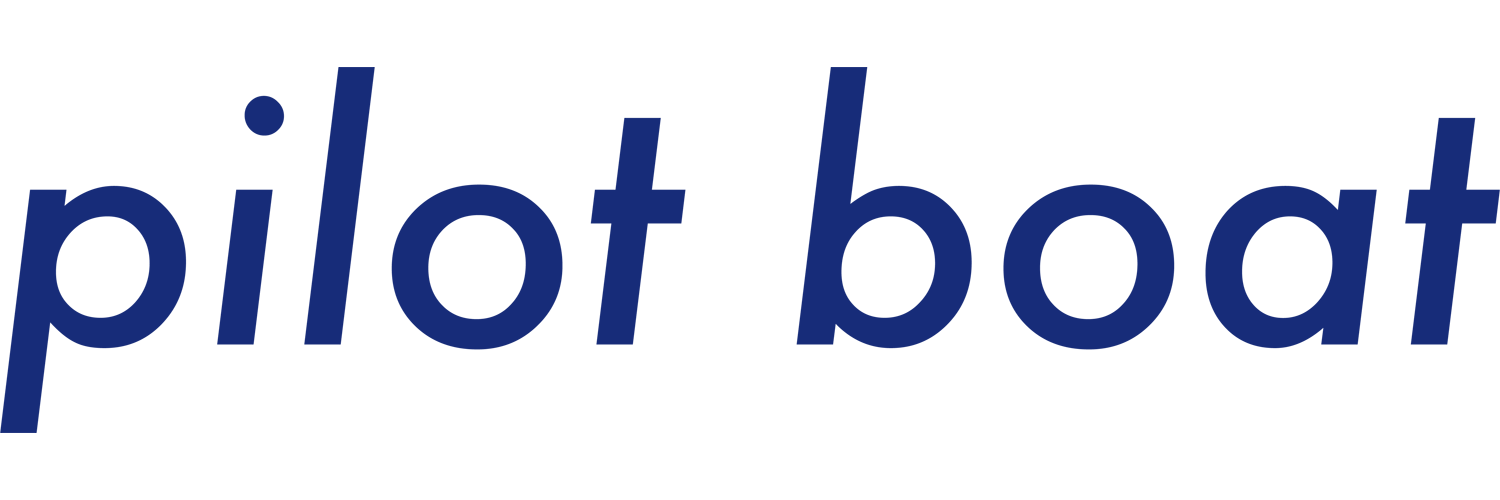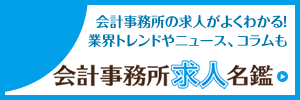2012年6月、中国・春秋戦国時代を舞台に、大将軍を目指す少年と天下統一を目指す少年王の活躍を描いた原泰久さんの人気マンガ「キングダム」のテレビアニメの放送がスタートしました。
皆さんは、それを記念して企画された「ソーシャルキングダム」をご存知でしょうか?
「ソーシャルキングダム」は、「キングダム」題材にして、読者が1人1コマずつ描き連ねて1つのマンガを完成させるという参加型のWEB企画です。この企画は、「史上最多人数で描きあげたマンガ」として、ギネス世界記録に認定されていて、マンガを手掛けた人数は1087名に及んでいます。
では、完成した「ソーシャルキングダム」の著作権はどうなっているのでしょう?
実際は、さまざまな契約によって権利処理されているのですが、今回は何の権利処理もされていない前提で考えてみましょう。
1.複数の人でマンガを描いた場合の著作権
「マンガは著作物であり、漫画家は著作権を持っている。」というのは一般的に理解されていることかもしれません。 しかし、それが複数の漫画家の合作だった場合、誰がどのように著作権を持っているのかについては、少し首を傾げてしまう方もいるのではないでしょうか。1つの著作物を2人で創作して、それらが個別に利用できないような場合、その2人が著作権を一緒に共有することになります。
このように複数人で共同創作した1つの著作物は、「共同著作物」と呼ばれます(著作権法2条1項12号)。そして、その共同著作者は、全員の合意を得なければ著作権を行使できないことになっています(著作権法65条2項)。
これに対して、複数人がそれぞれ創作した複数の著作物を、合わせて1つの作品を作ることも可能です。
このように色々な著作物が合わさってできた作品は「結合著作物」と呼ばれます。結合著作物は、全体として1つの著作物というわけではありません。著作物がいくつも集まって、全体として1つの作品を作り上げているという状態です。したがって、それぞれの著作者が自由に各自の著作権を行使することができます。
では、複数の漫画家が合作して1つのマンガを作成した場合、出来あがったマンガは「共同著作物」なのでしょうか、それとも「結合著作物」なのでしょうか。
これを考えるために、マンガを構成する要素がどんなものかを考えてみましょう。
マンガには、ストーリー、セリフ、コマ絵という要素があります。これらは、言語の著作物(ストーリーやセリフの部分)と美術の著作物(絵の部分)というように、それぞれが独立して著作物になり得るものです。そして、それ自体を分離して利用することも可能でしょう。
例えば、人気の1コマのコマ絵だけを絵やジグソーパズルにして、販売することをイメージして頂けると分かりやすいかもしれません。
そうすると、マンガは1コマごとに独立した著作物で、その1コマの中にも、セリフの部分とコマ絵の部分はそれぞれ違う著作物になっていて、集合して1つの作品が出来上がっていると言えそうです。したがって、複数の漫画家が合作して1つのマンガを作成した場合、そのマンガは「結合著作物」といえるでしょう。
ソーシャルキングダムは、1087人もの読者が1コマずつコマ絵を描き連ねた作品です。ということは、そこには1087個の著作物が集まっていて、それらが結合して1つの作品を作り上げているということになります。
2.原作との関係
では次に、「ソーシャルキングダム」と、原作である「キングダム」との関係を考えてみましょう。
「ソーシャルキングダム」はたくさんの著作物の集合体ですが、それらはもともとの1つマンガ「キングダム」を題材にして創作されたものです。このように、何かの著作物を題材にして新たな著作物が創作された場合、新しい著作物を「二次的著作物」といい、題材となった著作物を「原著作物」といいます。
そして、原著作物の著作者は、二次的著作物の著作者が有するものと「同一の種類の権利」を有しているとされています(著作権法28条)。
「同一の種類の権利」を有しているは、どういうことでしょうか?
これは、二次的著作物を利用する場合、二次的著作物の著作者の許諾のほか、原著作者の許諾も必要になることを意味します。二次的著作物は、原著作物をもとにして新しい表現を創作しているという関係にあるので、そこには原著作者と二次的著作者の2人分の権利が含まれているというイメージです。「ソーシャルキングダム」は1087個の二次的著作物の集合体ですから、その1087個の著作物の中に、原著作者と二次的著作者の2人分の権利が含まれていることになります。
この1つの作品にとてもたくさんの人の表現が詰まっていることを、改めて実感できると思いませんか?
「ソーシャルキングダム」のように、1つの作品や広告を元にしてWEB上で投稿型のキャンペーンをする「ソーシャルキャンペーン」は、近時注目されている広告手法です。
そのような「ソーシャルキャンペーン」を、少し目線を変えて著作権の視点から見てみると、意外と面白い見え方をするのかもしれません。
【執筆者】 弁護士 藤江大輔
※本記事はIT著作権.comからの転載記事です。